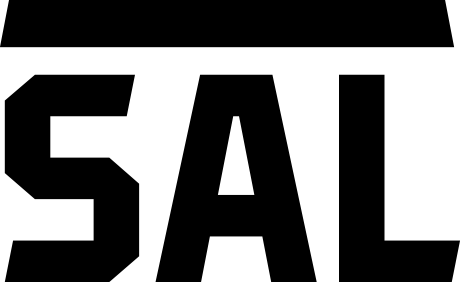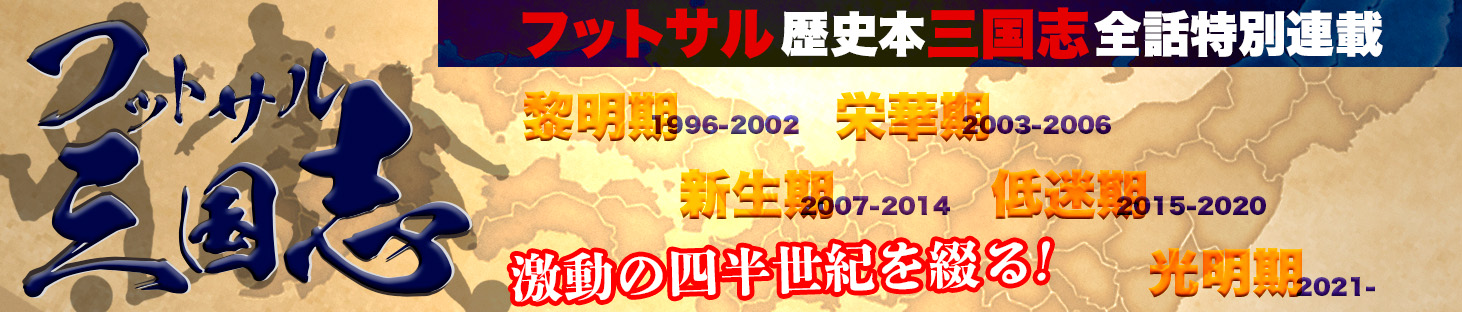更新日時:2025.09.04
【バーモントカップ】元町田・二井岡嵩登が「フットサル選手を目指すきっかけ」となった大会で伝えた、指導者としてのメッセージ「この大会でしか得られない必要な経験がある」

PHOTO BY本田好伸
8月15日から17日に行われたJFA バーモントカップ第35回全日本フットサル選手権大会が行われた。今大会に出場した広島県代表の福山ローザス・セレソンでコーチを務めていたのが、二井岡嵩登だ。
元ペスカドーラ町田の選手であり、現在は「日本一のカットインを持つ男」として、パーソナルトレーニングやYouTube配信など、多岐にわたる活動を通してフットサルの技術や価値を伝えている。
二井岡は、自身がサッカーを始め、中学まで所属したファースト・クラブのOBとして、ベンチに帰ってきた。今大会で監督を務めたのは父・秀敏さん。親子でベンチに座り、チームの指揮を執った。
福山ローザス・セレソンは、バーモントカップの“常連”の一つであり、2011年、2012年、2021年(※大会中止)、2023年に続き、今年、5回目の全国出場を果たした。それでも二井岡は「壁はある」と言う。
自身が「フットサル選手を目指すきっかけとなった大会」と語るバーモントカップで、彼は子どもたちに何を伝え、子どもたちに何を求め、そして育成年代におけるフットサルに、どんな未来を描くのか。
大会初日に試合会場で話を聞いた。

フットサル選手を目指すきっかけとなった大会

──このチームは二井岡さんの出身の……?
はい、僕が育ったチームで、父親が監督として見ているチームなんです。広島のチームなので僕は普段から子どもたちのことを見られているわけではないですが、全国出場するということで帯同させてもらいました。
──普段はどのくらいの関わりがありますか?
実家に帰った際に指導をさせてもらうこともありますが、それほど多くはありません。ただ、フットサルの大会ということもあるので、父親に「力を貸してくれ」と言ってもらえたのでありがたく引き受けることにしました。
──広島県出身だったんですね。
そうなんです。高校から兵庫に行きました。
──このチームではいつまでプレーを?
僕らの代からスタートしたので、実は一期生で、そこから中学3年生までずっとやっていました。
──そうなんですね。サッカー一家という感じだったんですか?
そうですね。父親がサッカー好きでしたし、僕も弟も物心ついた時からボールを蹴っていました。
──チームにはいつから帯同されていますか?
大会前日からです。そこでペスカドーラ町田U-12と練習試合をさせてもらいました。
──二井岡さんは毎年、この大会をチェックされているんですか?
バーモントカップは欠かさずに見ていますね。実は、僕がフットサル選手を目指すきっかけとなった大会なんです。小学6年生の時に広島県予選に出場して、サンフレッチェ広島U-12との決勝に敗れて全国には行けなかったのですが、フットサルのおもしろさを体感しました。広島ではフットサルをやれる環境は多くないのですし、フットサル選手を目指すきっかけにもなりますから、全国へとつながる大会があることは本当にありがたいですね。
──こうして大会に戻って来たことも感慨深いですね。
本当にそう感じます。感慨深いですし、指導者として戻って来られたことはありがたいですね。
サッカー選手に最初に伝えるフットサル要素とは?

──日頃、指導者として子どもたちに教える機会は多いですか?
けっこうありますね。子どものスクールや地方のフットサル教室などで見させてもらっています。子どもたちがもう少しフットサルを学べる環境をつくりたいと思って活動をしています。
──二井岡さんがそうであるように、バーモントカップは「きっかけになる」大会。フットサルと出会うことはもちろん、サッカーに生かす上でも有効な競技です。まず、どんなことを伝えるのでしょう?
やはり「勝ちたい」となると、とにかく相手のゴールに向かって蹴って、競り合う機会は増えるのですが、それがその先、子どもたちの成長につながるかどうかを考えないといけないと思います。この大会は、もちろん「勝ち」にはこだわらないといけないですけど、そのなかでもフットサルの要素を少しでも入れてやらないともったいないなという気がしています。
今日も子どもたちに伝えたのは、いきなり難しい戦術やフットサル要素を入れてもパンクしてしまうので、フットサル特有の「セットプレー」でしたね。狙ったプレーを、4人全員が連動してやってみよう、と。そうしたチームプレーをメインに伝えました。個人技のところはここまで積み重ねているものがあるので、自由にやってみようと。
チームプレーで言えば、守備の決まりごともそうですね。守備のマークは一人がずれてしまうと失点してしまうので、そうしたところは強く伝えました。
──サッカー指導者の場合は特に、最初に何を伝えるかで迷うこともあると思います。全国に勝ち上がってくるチームの実情としても、フットサルに特化した練習を日頃から長期間、積み重ねるケースは多くないようです。
指導者によっては、「まずは足の裏を使おう」と言って入る方も多いようですが、フットサルに特化したチームであったり、選手を輩出したいチームであったりする場合は、そうしたこともすごく大事だとは思います。
一方、多くがそうであるように、サッカーの延長線で出場してくるチームの場合は「足の裏を使おう」と言っても、限られた練習の中でそこに使う時間がもったいないと感じるケースもあるようです。なので、僕はまず「2人組の関係」を伝えます。
フットサルはどんな局面においても2人組以上の関係が必要になってくるので、ワンツー、パラレラ、ピヴォ当てなどももちろんそうですね。これらはサッカーでも生かすことができますし、ブラジルなどの選手は当たり前の感覚として小学生年代からやっているので、そういうところはフットサルを利用して練習に取り入れると、選手のレベルアップにつながるのではないかと考えています。
育成年代のサッカー選手が経験すべきこと

──実際に参加して感じる子どもたちの変化はありますか?
大舞台に緊張していて普段通りのプレーができていないというのはあるのですが、子どもたちも、「指示がサッカーよりも細かい」「一瞬、一瞬のプレーで状況が変わるから常に集中して周りの声を聞いておかないといけない」といったことを話していました。そうした張り詰めたなかで1試合を戦うというのは、サッカーとは異なる部分だとも思いますし、そこが子どもたちにとっても大きな刺激になっているように感じます。
──指導者が試合に関与できる要素が多いのもフットサルですよね。「自由すぎない」ことは、ある意味でこの年代の選手にとってもプラスになる部分はあるのではないでしょうか。
自由にやらせてあげたい気持ちもありますけど、フットサルでは、自由にやりすぎてしまうとグダグダになったり、失点してしまったりするので、ある程度の「規律」や「規則性」を伝えています。
ただ、すべてのことにおいて指導者が指示して動かしてしまっては子どもたちにとってはおもしろくはないと思いますし、ロボットのようになってしまいますから、難しいところですが、そこは気をつけながら伝えています。
──初戦では、フィクソの位置で追い込まれて、そのままゴールに押し込まれてしまうシーンがありました。底辺で奪われて即失点する経験もある意味で大きいだろうなと感じました。
そうですね。フットサルならではのシーンだったと思います。一つのミスが本当に命取りになるという。選手もそれを経験できたことでその後の対応を変えることができていました。失点してしまいましたけど、この大会で必要な経験になるのではないかと思います。
──二井岡さん自身の今大会のテーマはありますか?
本来であればもっと練習から関わってこられたら良かったですけど、全国大会は指導者としても大きな経験になる舞台です。
本当に一瞬の指示のミスでやられてしまうこともあります。予選や練習試合とは異なりますし、タイムアウトを取るタイミングもそうですけど、試合時間も大人よりもずっと短いですから、瞬時の判断を意識してやっていきたいな、と。僕自身、指導者として初のバーモントカップを楽しめたらと思います。

▼ 関連リンク ▼
- 【最新情報】JFA バーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権大会|試合日程・結果・順位表|試合会場|日本サッカー協会
- マルバ千葉が小学生年代日本一の悲願達成!決勝でトリアネーロ町田に10-3で大勝、世代屈指の強豪“マルバ勢”としては2007年以来18年ぶり優勝|フットサル/バーモントカップ
- マルバ千葉fc・高越啓資「誰にも止められない選手になりたい」7試合25点で大会得点王、圧倒的エースが目指す選手像|バーモントカップ/フットサル
- マルバ千葉fc・大内波論「弾くボールをどうつなげるか」攻守に輝くオールラウンダーが見据える、一手先の守備|バーモントカップ/フットサル
- マルバ千葉fc・佐藤篤志「試合中に気づきが出てきた」2大会連続出場の主将が、決勝戦で体現した"マルバのフットサル”|バーモントカップ/フットサル
- U-12年代日本一、上田綺世を輩出したマルバ千葉の育成哲学とは?父・智久監督&息子・葵コーチ、浅野親子が語るサッカー、フットサルの指導者が心がけるべきこと